星

変光星と若い天体
ソラジオトークfrom OKAYAMAへようこそ 変光星と星の誕生を主に研究しています。岡山理科大学の福田です。
今回のテーマは、「変光星と若い天体」でしたね。
放送分で解説したように、光り輝く星、恒星。
この恒星の中でも明るさが変わる星があります。
これを変光星と呼んでいて、今までに223万個以上の変光星が発見されています。
まず、太陽がどのようにして誕生したのかをお話しします。
太陽は分子雲と呼ばれるガス雲が重力によって集まり、収縮して誕生したと考えられています。
ものが集まってくると、圧力と温度があがっていきます。
この状態で光っている星を前主系列星といいます。
その後、重力収縮がさらに進み、中心の温度がさらに上がると、中心部では水素の核融合反応が始まります。
この状態の星を主系列星と呼びます。
現在の太陽も水素の核融合反応で光る星で、主系列星に分類されています。
先ほど、太陽の誕生の説明をしましたが、おうし座T型星はこのような天体の代表例です。
変光星には色々な種類がありますが、その種類に応じて、代表星の名前に型をつけて、なになに型と呼んでいます。
つまり、おうし座T星を代表とした変光星の種類を、おうし座T型星と呼んでいます。
おうし座T星は、おうし座にある変光星で、ヒアデス星団のV字型を型作る最も北の星の近くに位置します。
年齢は、数百万年の非常に若い天体で、地球から471光年の距離にあります。
おうし座T型星 前主系列星は大変面白い特徴を持っています。
地球や木星など惑星を育む円盤の構造が存在し、最新の電波望遠鏡でその姿が調べられています。
ジェットと呼ばれるガスの噴出現象も観測されています。
おうし座T型星自身も様々な理由で、星の明るさを変化させます。
太陽も現在の状態になる前はいろいろなことが起こったと考えられます。
さて、ここからは、さまざまな種類がある変光星の中で、重要な天体についてご紹介します。
天文学の歴史上、もっとも重要な変光星の型は、問題の選択肢にあったケフェウス座デルタ型星です。
ケフェウス座デルタ型星はセファイドあるいはセファイド変光星ともいいます。
この変光星では星自身が周期的に膨張と収縮を繰り返す「脈動」によって、その明るさが変化します。
脈動の周期と、天体の真の明るさに関係があることが発見されたため、銀河系近傍の銀河の距離を測定することに使われました。
ハッブル=ルメートルの法則として知られている、宇宙膨張の法則は、こういった脈動変光星の観測によって発見されたのです。
最近、宇宙は加速膨張しているといった話を聞いた人もいるかと思います。
宇宙の加速膨張を調べた研究も変光星を用いて調べられました。
その変光星はIa型超新星と呼ばれる天体です。
Ia型超新星の正体は連星系をなす白色矮星の爆発で、爆発の仕方がいつも同じであるため、その明るさもいつも同じであると考えられています。
このことから遠方の銀河の距離を測定することに、Ia型超新星が使われました。
ただ、このIa型超新星となる直前の状態に関しては、まだ研究途中でよくわかっていません。
2つの白色矮星が合体して爆発する説。白色矮星の隣の星から質量が降り積もって爆発する説があります。
もう一つの選択肢にあったアンドロメダ座Z型星は将来Ia型超新星をおこすかもしれない変光星です。
アンドロメダ座Z型星の光を調べてみると、高温の星雲と、低温の恒星といった、熱い天体と冷たい天体の両方の特徴が見られます。
2つの特徴が共存していることから、共生という言葉が使われ、共生星と呼ばれています。
共生星は、白色矮星と巨星からなる連星であることが知られており、Ia型超新星へと進化する候補天体として、現在注目されています。
星は一つ一つ距離が離れていて、それぞれ特徴を持っており、様々な観測をすることで、新たなことがわかってきます。
岡山理科大学で一緒に学んでみませんか?
以上解説は、岡山理科大学の福田でした。

地球から見た星の明るさ「等級」「〇等星」「星の色」
問題の「次のうち、一番明るい星はどれか。」で、正解は―3等級でした。
地球から見た星の明るさは等級で表します。
古代ギリシャの天文学者ヒッパルコスが肉眼で見える星を明るい順に1等星から6等星と決めたのが始まりで、数字が大きくなると暗い星を表します。
そしてイギリスの天文学者ハーシェル親子とドイツの天文学者ポグソンによって、星の明るさと等級の関係が調べられ、1等星と6等星では平均の明るさが約100倍違うことがわかり、明るさの尺度である等級は、1等級の差が約2.5倍の明るさの差に相当するとして細かく表せるようになりました。
全天で最も明るい星を1等星と呼びますが、皆さんいくつくらいご存知でしょうか。
春には、うしかい座のアークトゥルス
夏には、こと座のベガ
秋には、みなみのうお座のフォーマルハウト
そして、冬の夜空に輝くおおいぬ座のシリウスなどがあります。
1等星の数は全天で21天体、1等星から6等星までの星の数は全部で約8600個あります。
ただし、これは全天の数であり、地平線より上だとその半分、さらに地平線すれすれの星はみえないと考えると、だいたい3000個ぐらいになります。
暗い星は肉眼では一般的に6等星までしか見えませんが、双眼鏡や望遠鏡などを使用することでさらにくらい星まで観察することができます。
さて、これらの1等星ですが、実際にはすべて同じ明るさではありません。
例えば1等星の中でも一番明るいと知られている、シリウスは見かけの等級は-1.5等ですが、こと座のベガは0等でシリウスの方が明るい星となります。
シリウスは地球から8.6光年の距離にあり、ベガは地球から25光年の距離にあります。つまりベガの方が地球から離れた位置にいることになります。
星の明るさは、距離の2乗に反比例することから地球から近い距離のシリウスの方が明るく見えてしまうことが考えられます。
そこで、星を地球から32.6光年の距離に置いた時の明るさで比べてみると、シリウスは1.4等、ベガは0.6等とベガの方が明るいということが分かります。
このようにすべての星を地球から32.6光年の距離のところにおいた時の明るさを真の明るさとして、天文学では絶対等級と呼び絶対的な明るさの指標にしています。
このような星たちを観察していると、明るさの違いだけでなく色の違いがあることに気づくと思います。
星の色は星の表面温度を反映したもので、温度が高いほど青白く、温度が低いほど赤っぽい輝きとして見えます。
たとえば、さそり座のアンタレスのように赤い色をした星から、ぎょしゃ座のカペラのように黄色い色をした星、シリウスやスピカのように白い色をした星があります。
実際の星の温度は
赤い色をしたアンタレスの表面温度=約2500℃
黄色い色をしたカペラの表面温度=約6000℃
青白く輝くスピカの表面温度=約12000℃
もっとも身近な星である太陽の表面温度=約6000℃であるため、黄色い色をした星といえます。
地球上からは、暗すぎて色が分からない星も天文学の研究の一つである。光をプリズムなどを通して色ごとにわける分光という方法で調べると
星の大気の温度、星を作っている元素がどのようなもので、どれくらい含まれているかなど、いわば星の個性をあつめるような研究で調べることができます。
解説は、日本スペースガード協会 安藤さんでした。

最も表面温度の高い星は何色?
「最も表面温度の高い星は何色?」でしたが
夜空にはたくさんの星が輝いています。これらの星をよく見比べると、赤い星や黄色い星、青白い星など、いろいろな色の星があることに気が付くと思います。
例を挙げると
「春」春の大曲線をつくる1等星「アークトゥルス」がオレンジ色の星
おとめ座の1等星「スピカ」が青白い星。その色から麦星、真珠星と呼ばれていました。
「夏」さそり座の1等星「アンタレス」が赤い星。
こと座の1等星「ベガ」が白い星。このベガは七夕の織り姫星としてよく知られています。
「冬」オリオン座の左肩にある1等星「ベテルギウス」が赤い星。右下の1等星「リゲル」が青白い星。
すぐ近くにある、ぎょしゃ座の1等星「カペラ」は黄色い星。
このように様々な星の色があるのはなぜでしょうか?
何が星の色を決めているのでしょう?
皆さんは、鍛冶屋さんが鉄を真っ赤に加熱してハンマーで力強くたたいている場面をテレビや動画で目にしたことはありませんか?
十分に加熱した鉄は、まぶしいほど白っぽく光っていますが、作業をしてだんだん温度が下がるとともに黄色くなっていき、そのうち赤黒い色に変わっていきます。
このように、物体の色は、温度と関係があるのです。
物体の温度が低いときは、波長の長い赤い光がもっとも強く出ていて、温度が高くなるほど、波長の短い青い光が強く出るようになっていきます。
これは、星の場合も同じです。
星の色が赤からオレンジ、黄、白、青白となるにつれて星の表面温度が高くなっていきます。
おおまかにいえば、赤い星アンタレスの表面温度は、約3500度
オレンジ色のアルクトゥルスは約4000度、黄色い星カペラは約6000度です。
さらに、白い星ベガは約9500度、青白く光るスピカは約12000度という高温です。
太陽の表面温度が約6000度なので、黄色い星といえます。
星の色を観測することによって星の温度を知ることができるのです。
ちなみに、温度が低いほうの話もしておくと、宇宙空間の平均温度は、マイナス270度といわれています。
この温度も空間からの電磁波を測定することによって知ることができました。
宇宙は無数の恒星からのエネルギーで熱くなりそうなものですが、地球でいえば地表や雲や大気のようなエネルギーをしっかり受け取る物質がないために温度が上がりません。
光についてもう少し詳しく説明すると
光には波の性質があるのですが、水面の波や音などとは違って真空中を伝わることができます。宇宙で輝いている星は、非常に高温の気体の巨大なかたまりで、その表面から熱や光を出しています。こうして出た光の波は、真空の宇宙空間をはるかかなたの地球まで伝わってきます。
私たちがみているのはその光です。
私たちの目は、光の波の細かさを虹の色のようにさまざまな色としてとらえることができます。波の細かさを波長といいますが、長い波長の光はオレンジ色や赤色に見え、短い波長の光は青や紫色に見えます。星が出している光にはいろいろな波長の光が含まれていて、それぞれの強さや混ざり具合に特徴があり、これをスペクトルといいます。
スペクトルを詳しく調べることによって、星の表面温度の違いや、含まれている物質の種類などを知ることができるので、星をきちんと分類することができるのです。
人は、どのようにして色の違いを見分けているのかを簡単に説明します。
太陽や電球のように、光を出している物体を光源といいます。
多くの場合、光はいろいろな波長の光を含んでいて、それぞれの波長に応じた色があります。
一方で、いろいろな光の色を「光の三原色」と呼ばれる、赤、緑、青の光をいろいろな強さで組み合わせて作ることもできます。
私たちの目の奥にある網膜には、光を感じる2種類の細胞があり、ひとつは光の明るさを感じる細胞、もうひとつは、特定の光の色の強さを感じる細胞で、光の三原色である赤、緑、青に対応しています。
これらの細胞が感じた光の信号の強さを脳で処理して、異なった色として感じているのです。ちなみに、テレビやパソコン、スマホの画面では、赤緑青3色の細かい点が光っています。虫眼鏡やルーペで見てみるとおもしろいですよ。
星からの光を調べる際に重要なのが、スペクトルですが、これは光を分解して、どの波長の光がどれくらい含まれているかを示すものなので、私たちの目と脳が行っている作業を観測装置で行うようなものなのです。
さらに、スペクトルの中にある輝線とよばれる特に明るい部分や、暗線と呼ばれる暗い部分などの様子からどんな物質が光を出しているのかも分析できます。
当然、これらは目で見たのではわかりません。
身近なものとしては、太陽の光、白熱電球、蛍光灯はそれぞれ特徴のあるスペクトルを示します。
実際の観測では、その星が何万光年も離れていても、届いた光のスペクトルを分析することで、その星の温度や光を出している成分、近くに存在するガスの成分などを調べることができるので、その星にどのようなことが起きているかを推測できます。
このようにスペクトルにはたくさんの情報が含まれていて、宇宙の謎を解明するための重要な手がかりなのです。
解説は、岡山天文博物館 大島さんでした。

天の川銀河には何個ぐらいの恒星、つまり星があるか。
問題「天の川銀河には何個ぐらいの恒星、つまり星があるか。」でしたが、正解は、2000億個でした。
天の川銀河について詳しく解説をしていきます。
我々は、太陽系が属する銀河・天の川銀河を内側から眺めて、夜空を横切る淡い光の帯「天の川」として観測しています。
太古の人々は雲のように見えるその存在を、何千億の星々が重なり合った存在であることは、知る由もありませんでした。
天の川が星の集団であるということを明らかにしたのは、今から400年以上前のイタリアの科学者・ガリレオ・ガリレイです。彼は、自作の望遠鏡を天の川に向け、天の川が無数の星の集まりであることを発見しました。
天文学者は天の川の星を完璧に数えると、この宇宙の形や大きさがわかると考えました。ガリレオ以降の200年間、天の川の研究は当時の最先端のテーマだったのです。
18世紀、イギリスの天文学者・ウィリアム・ハーシェルは、夜空の星の数をくまなく調べ上げて、我々の太陽系は、凸レンズのような形をしている星の集団の中にあることを初めて示しました。現代に通じる天の川銀河の姿を明らかにした、最初の研究成果です。
しかし、当時の観測技術では、確認できる星の明るさには限界があって、ハーシェルは天の川銀河という星の大集団の、ごく一部しか観測できていなかったことが、後々、明らかになります。
ハーシェルが見積もった天の川銀河の大きさは、6千光年。実際の天の川銀河の直径は、それより20倍も大きく、10万光年を超えることがわかっています。
18世紀、望遠鏡の性能が上がってくると、星雲と呼ばれる星々の間で見つかる淡い雲のような天体の中に、ガスの雲のような種類のものと、渦を巻いたような整った姿をしているものがあることが分かり始めました。
のちに銀河と呼ばれる後者の種類の星雲が星の大集団であることがわかると、この天体の正体がなにものであるかという議論が活発化していきます。
おおむね200年以上前の天文学は、天の川銀河という星の集団全体が、宇宙そのものであって、すべての天体は、この中に浮かんでいる存在であると考察されていました。星の大集団の中に、星の大集団が浮かんでいるという姿に違和感を感じる天文学者も少なくなかったと思われます。
そして、20世紀に入り、写真によって天体の明るさを正確に計測したり、分光と呼ばれる天体の光の特徴を詳しく調べる技術が確立されると、こうした天体のおおよその距離が測れるようになってきました。
得られた銀河までの距離は、天の川銀河の直径よりはるかに大きい。つまり、すべての銀河は天の川銀河の外に存在していることが明らかになりました。
この宇宙には銀河と呼ばれる星の大集団が無数に浮かんでいて、我々の太陽系を含む銀河も、そうした銀河のひとつに過ぎない。人類にとっての宇宙のサイズは、このとき、一気に広がったのです。
今ではよく知られているこうした現代的な宇宙観つまり宇宙の本当の形を理解できるようになってから、人類はわずか100年程度の歴史しか持っていないというわけです。
天の川銀河に最も近いおとなりの銀河は、有名なアンドロメダ銀河。距離は230万光年。光の速さでも230万年かかる距離です。
そして、果てしなく広い宇宙の広がりの中には、数兆個の銀河が存在していると推定されています。銀河を詳しく知ると、壮大な宇宙のロマンを感じることができますね。
解説は、ライフパーク倉敷科学センター 三島さんでした。

地球に近い星団の話
問題「次のうち地球の一番近くにある星団は、どれか。」でしたが、正解は、ヒアデス星団でした。
地球からヒアデス星団までの距離は、およそ150光年で、年齢約6億年。
おうし座に位置する散開星団で、1等星アルデバランの近傍に広がるV字形の星の集団で、おうし座の顔の位置にあります。日本ではその形状から釣鐘星(つりがねぼし)と呼ばれて2007年には日本の国立天文台を中心とする研究グループによって、星団を構成するおうし座ε(イプシロン)星に木星のような巨大なガス惑星が発見されました。
次に近い、星団でおうし座のプレアデス星団は
地球から約400光年(よんひゃく)の距離にある散開星団です。日本では、「すばる」(昴)という和名でも知られています。この星団は地球に最も近いメシエ天体であり、最も明るい星団です。プレアデス星団は、燃焼が激しいため寿命が短く、あと1,000万年ほどで消滅するとの予想があります。
ケンタウルス座オメガ星団は
地球から約17,000光年(いちまんななせん)の距離にあり、約1,000万個の恒星からなる大型の球状星団です。明るさは3.7等級と明るく肉眼で見ることができる数少ない球状星団のひとつです。しかしながら、南の低い位置にあるため、冬のカノープスと同じく見るのが困難な天体で、もっとも高くのぼった時でも、地平からの角度が九州で約10 度、沖縄でも約15度にしかならず、カノープスと同じく関東より北の地域では見ることができません。この巨大球状星団は他の球状星団と異なる性質をもっていることがわかっており、そのことから、過去に、小型銀河がわれわれの銀河系により破壊され、その中心核部分が、このオメガ星団として残っている、との説があります。
最後に、M13は
ヘルクレス座にある球状星団です。ヘルクレスの胴体にあたるη(イータ)星とζ(ゼータ)星の間にあり、北天で最大かつもっとも美しい球状星団といわれています。太陽系から約22,000光年離れており、数十万個の星からなります。肉眼では星雲状に見えますが、双眼鏡や天体望遠鏡でみると、中心部の星が集中している様子がわかります。日本では南中するとほぼ天頂付近までのぼるため、条件の良い日には小口径の天体望遠鏡でも密集した星の様子を楽しむことができる見応えのある天体です。
解説は、日本スペースガード協会 西山さんでした。
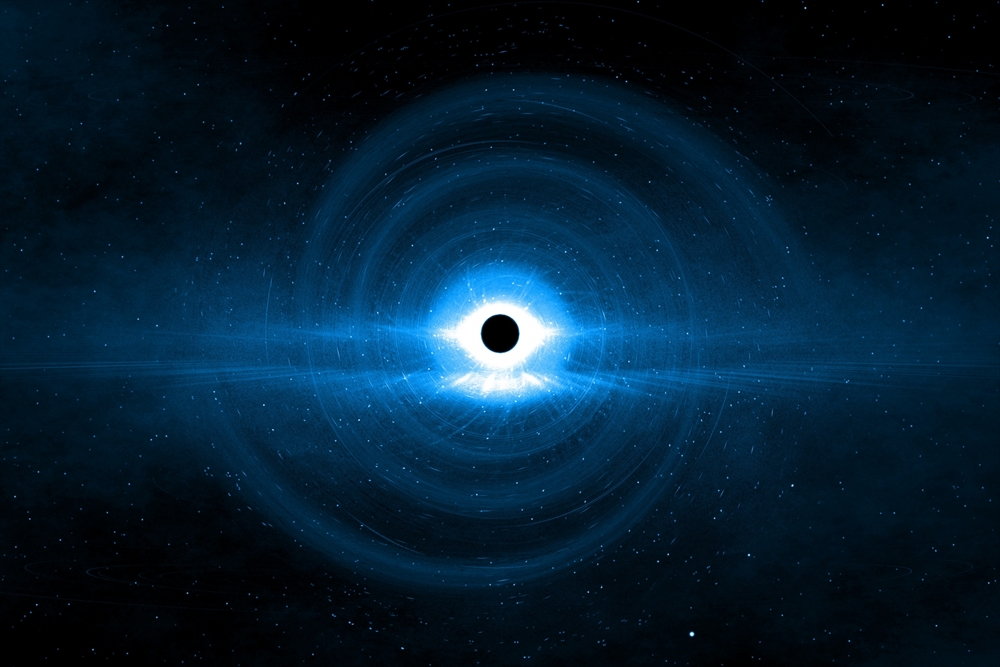
星が生まれる場所「暗黒星雲」とは何か?
問題にあった「ガスやチリが集まって星が生まれる場所を何と呼ぶか?」
正解は、「暗黒星雲」でした。
では、「暗黒星雲」とはどういった状態なのでしょうか?
星間物質中のチリ(ダスト)が天体からの光を吸収し遮ることにより、空の上で周辺より暗く(黒く)見える部分のこと。大きさは、望遠鏡でないと見えない1分角以下のものから目で見てもわかる数度角にわたるものもあり、その形状も不規則で多様です。
〇分角について※角度および経度・緯度の単位。1分は1度の60分の1。(Wikipediaより)特に天の川に沿って観測されます。
暗黒星雲には、低温度の星間物質が濃く集まっています。その主成分は水素分子で、チリ(ダスト)は1%以下です。典型的な水素分子密度は、1㎤あたり、1000ないし1万個で、温度は絶対温度10K程度です。※温度の単位の1つで、単位は [K] です。 「熱力学温度」と呼ばれることもあります。10K= -263.1500℃
質量は、太陽質量程度のものから、その1万倍以上のものまであります。電波観測から、暗黒星雲の中にさまざまな分子があることも知られています。このため、暗黒星雲は、「分子雲」とも呼ばれます。
ただし、暗黒星雲は、可視光での見え方によって定義されるのに対して、分子雲は、電波観測から定義されたものなので、その大きさや広がりは必ずしも一致するわけではありません。
分子雲があってもそれを照らす星がなければ暗黒星雲としては見えません。
暗黒星雲は、星形成領域にあり、しばしば、輝線星雲や反射星雲のような光って見える星雲と混在しています。
星は、暗黒星雲の中で生まれますが、可視光では、強い吸収のためにその様子はほとんど見えません。吸収の少ない近赤外線で見ると、暗黒星雲の奥深くで誕生したばかりの星々の存在がわかります。
また、さらに波長の長い中間赤外ないし遠赤外線でみると、星間物質中のダストから発する熱放射によって暗黒星雲が「輝いて」みえる。ハッブル宇宙望遠鏡などで、紫外線、可視光、赤外線を総動員して、高分解能の写真を撮ると、暗黒星雲の中で生まれた大質量星からの強力な紫外線によって、星間物質の一部が昇華して、密度の高い部分だけが柱状に残る構造や生まれたばかりの星からジェットが噴き出している様子などが見られます。
ちなみに選択肢にあった「アンドロメダ銀河」というと皆さん聞きなじみがあるかもしれませんが、アンドロメダ銀河は、地球から約250万光年離れている場所にあります。
ということは
私たちがみているアンドロメダ銀河はおよそ250万年前の姿だということになります。日本では、秋ごろに見ることができます。
また、「天の川銀河」と「アンドロメダ銀河」の距離は縮まっていて、アンドロメダ銀河は約40億年後に天の川銀河にぶつかると考えられています。しかし、お互いをすり抜け、一度は通り過ぎた2つの銀河は、お互いが引っ張り合う重力に引き戻され、最終的には、2つの銀河の銀河核は融合します。
このように銀河というのは、衝突や合体を繰り返すことによって進化していくと考えられています。
では、この時、我々人類はどうなっているか?
この衝突が起きるころには、太陽は、「赤色巨星」という大きな星になって、金星の軌道上に達するほど膨張し、地球の温度は、現在の「水星」並みの約430度となり、灼熱の星となってしまい、人類はもはや、地球に住むことができなくなっているでしょう。
解説は、日本スペースガード協会 奥村さんでした。
協力
Copyright © 2022 OKAYAMA FM Inc. All rights reserved.